伝統技能を
「藝」として昇華する
「福岡藝賓館」は、職人の技能を「藝」として継承し、発信し、もてなす住宅兼迎賓館。左官職人を原点とする建設会社として、失われつつある伝統建築の基層−素材・技術・思想−を、時代に即した形で再解釈・再構成。かつて福岡に存在し、大陸との文化交流の場であった「鴻臚館(こうろかん)」になぞらえ、地産素材と職人との協働により、未来にひらいた建築が誕生しました。
Hospitality made possible
through traditional
Japanese skills
「福岡藝賓館」は、職人の技能を「藝」として継承し、発信し、もてなす住宅兼迎賓館。左官職人を原点とする建設会社として、失われつつある伝統建築の基層−素材・技術・思想−を、時代に即した形で再解釈・再構成。かつて福岡に存在し、大陸との文化交流の場であった「鴻臚館(こうろかん)」になぞらえ、地産素材と職人との協働により、未来にひらいた建築が誕生しました。
Mission
伝統を未来につなぐ問いから生まれた「福岡藝賓館」は、探求・継承・発展を軸に、次世代育成や地域文化・産業の活性にも寄与する新しい建築像を提示しています。
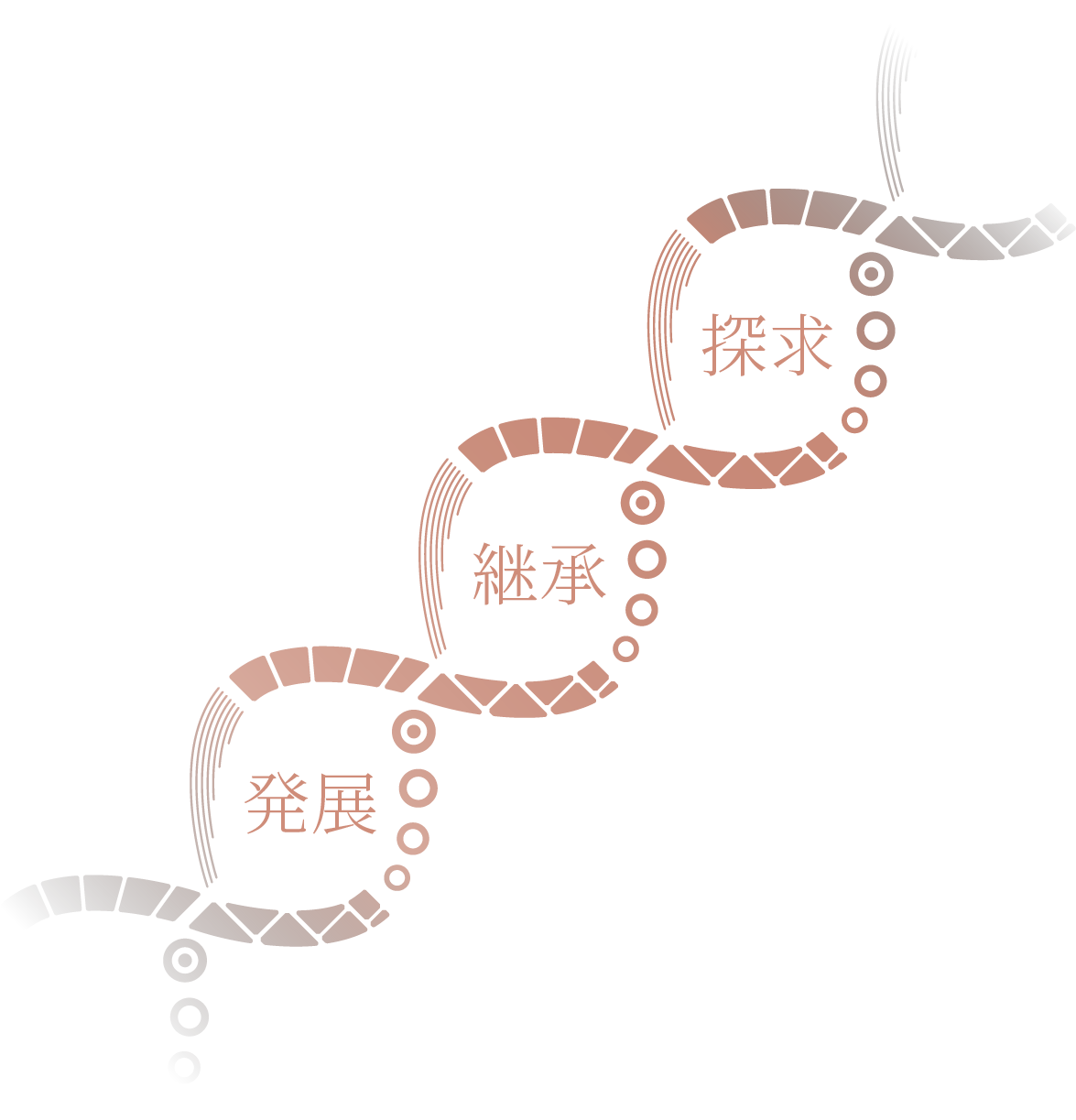

Architecture
敷地形状に呼応するように弧を描く石垣は大島石(愛媛県)の皮肌。相方積みによって再構築された石組みは、地域のシンボルであった旧宅の「大きな石垣の家」という面影を残し地域の記憶を継承し風景に溶け込むように計画しました。擁壁の上には杉板を用いた打放コンクリートのボリュームと白漆喰のボリュームを対比させ日本の建築様式を現代的に表現しています。夜間もライトアップを行うことで大島石の石組みと併せ地域のシンボルとなっています。
個人邸でありながら迎賓館としての機能も備えているため、地下のエントランスは「おもてなしの空間」を演出しています。入口では大島石の巨石とアルミ鋳造の大型門扉が来館者を迎え、車路は弧を描く大島石の壁と一部に旧宅の石を再利用した床で構成。館の玄関を兼ねるため一部の壁に突板を用い、柔らかい間接照明によって居住空間と同様の演出を行なった。吹抜けのホールは福岡県を中心に九州・全国各地から探し集められた材料によって仕上げられた。


ひとつながりの空間に使い方やシーンの異なるエリアが連続するパブリックスペース。視線をずらすエリアの組み合わせや家具レイアウトと素材を選択することで用途と領域を形成し、質の異なる空間が折り重なることで奥行きのある空間が構成されています。有田焼のタイルを敷き詰め空間に連続性を持たせたことで内部と外部がシームレスに繋がり、回遊性と開放性を両立。和室では3次元の曲面を持つ天井を白漆喰、床間の壁を高い技術が求められる黒漆喰で仕上げています。
3階は住居。家族間のふれ合いを促しながら、互いのプライバシーを保った平面空間となっています。大理石のゲートを持つエレベーターホールをコアとして家族の集まる空間を構成。開放的で伸びやかなダイニングとリビングは、大きな空間で異なる使い方ができるよう家具と折上げ天井により緩やかに二分され、壁は左官壁と真鍮目地を配したクリの突板で構成されています。また、隣地の視線と道路の騒音からプライベートな空間を守るよう外周に設けられた壁は、十分な採光も確保された外部との緩衝帯となっています。
